高校生向けオンラインセミナー(3)

10月23日 順天堂大学
天野篤 特任教授(心臓血管外科)/山本祐華 准教授(産婦人科)/田端実 主任教授(心臓血管外科)/中西啓介 准教授(心臓血管外科)
医師ってなに?
順天堂大学の医師4人は、目指すべき医師の姿や心構えなどについて講義した。
2012年の上皇さまの心臓手術を含め、これまでに約9300例を執刀した心臓血管外科の天野篤特任教授は、医療の歴史や国民皆保険制度の概要を説明。コロナ下の現在でも、医療が、日常の生活や経済活動を支える社会基盤として重要であることを示し、「医師には医学で多くの人を導いていく使命がある」と語った。
現代医療は、エビデンス(科学的な根拠)に基づいて診断・治療を行い、常に患者の安全を最優先すること、その上で痛みや患者の心身への負担がより少ない治療法を目指すことが大事だと強調。「心臓手術は1000例までは患者から教わることが多く、3000例で一人前」などと、技術を磨き続けてきた経験を振り返った。
患者の命を預かる仕事だけに「中途半端な気持ちで医療の世界に入ってきてほしくない」と話し、医師を目指すのであれば、心構えとして「感謝」「祈り(信じる心)」「応援」「根拠に基づく自信」を持ち続けてほしいと訴えた。
山本祐華准教授は、自らが産婦人科を選んだ理由について「女性を生涯通して診ることができて、女性として役に立てるから」と話した。妊婦健診や帝王切開といった現場の様子を動画で解説。超音波などを使う事前診断によって、生まれてくる赤ちゃんの命を救うことができる胎児診断についても説明し、「チーム医療で、赤ちゃんと家族を笑顔にする。そこが魅力だ」と語った。
また、女性が医師になることについては、「体力はある程度必要だが、普通であれば乗り越えられる。出産した後、医師を続けている人も多い。これからはより働きやすくなるだろう」と述べた。
心臓血管外科の田端実主任教授は、医学部を卒業して5年後という早い時期に米国へ臨床留学したことが、より小さな手術の傷で体へのダメージを軽減した低侵襲手術と出合うきっかけになったと話した。
現在では、胸に小さな穴を開けて、そこから体に入れた内視鏡の画像を見ながら手術を行う完全内視鏡下心臓手術を実施。手がけた手術745例での入院日数は、半数以上が5日以内で、全国平均の14日よりはるかに短いというデータを示し「これが手術の進化。傷が小さいだけでなく、患者が早く社会に戻ることが出来るのが強み」と話した。
さらに早稲田大学と共同でカテーテル人工弁の研究開発にも取り組んでいると説明。「足りない部分の技術開発も行う。医師という仕事には、道しるべなどないので、自分で切り開くことが大事」と訴えた。
「今日は医師の仕事の一部を垣間見て欲しい」と切り出した中西啓介准教授は、小児心臓外科医の仕事を、実際の手術動画を見せながら解説。人工心肺装置など様々な機器やモニターが並ぶ手術室で、医師や看護師といった複数の医療スタッフが連携して治療に当たるチーム医療の様子や、子どもの患者が手術を怖がらないように明るく接し、入室の際にアニメを流す工夫をしていると説明した。
小児心臓外科医は、ほかの診療科の医師に比べて「仕事がきつい」「休みがない」「お金を稼げない」といった理由で成り手が少なく、学会誌などでは「絶滅危惧種」と言われていると紹介。厳しい仕事にもかかわらず続ける理由として「(治療をすることで)存在しなかったはずの、子どもたちの未来が見られるから」と述べた。
「医師の仕事は、人のためにすることを恥ずかしがることなく、思いきり出来ると思っている。医学部入学で終わることなく、その先に何をするのかが大事だ」とアドバイスした。
 |
| 順天堂大学のセミナーで天野特任教授に質問する都立戸山高校の吉田さん(右端、新宿区・戸山高校で) |
直接話聞き生徒の意欲高まる
一連のセミナーには、学校単位での参加が21校あった。このうち東京都立戸山高校(新宿区)では、10月23日に行われた順天堂大学のセミナーに1、2年生12人が参加した。
「医師として、これだけは譲れない、誰にも負けないものを教えてほしい」と質問したのは1年生の吉田圭汰さん。天野特任教授は「粘り強さ。あとは、指の間で感じる20ミクロン(マイクロ・メートル)ぐらいの触覚と(手術の)場数。道場剣法ではなく実戦剣法です」と答えた。吉田さんは「天野先生の経験のすごさが伝わる言葉だった。私も何か道を究められるような医師を目指したい」と笑顔を見せた。
同校は都立高で唯一、医学部を志す生徒向けの育成プログラム「チーム・メディカル」を導入。担当の松元智志教諭は「医師の話を直接聞くことで生徒の意欲が高まる」と話している。
10月29日 大阪大学
上野豪久 特任准教授(大学院医学系研究科 小児成育外科)/平将生 講師(大学院医学系研究科心臓血管外科)
移植医療を通じて命を考える
「臓器移植、あなたなら受けますか」「あなたが家族だったら、移植に賛成しますか」
小児心臓移植を専門とする大阪大学の平将生(まさき)講師は、生徒にこう語りかけた。
臓器移植は、誰もが受けられるわけではない。〈1〉ほかに有効な治療手段はないか〈2〉生命の危険が迫っているか〈3〉移植後の検査や薬に心身が耐えられるか〈4〉家族の協力が期待できるか──といった条件を厳密に検討する必要がある。条件がそろっても、臓器提供者がいなければ治療はできない。
移植手術をして終わりというわけではない。手術後は、拒絶反応を抑える免疫抑制剤の使用が欠かせない。だが、抑制剤は諸刃(もろは)の剣だ。拒絶反応ばかりでなく通常の免疫反応も弱めてしまうため、感染症の予防が大きな課題になる。平講師は「生涯をかけての治療・管理が必要になる」と治療の難しさを説いた上で、「しっかり管理すれば、しっかり生きられる」と強調。移植治療は脳死判定された人から臓器を譲り受ける「生命のリレー」であるとして、社会の理解が必要だと訴えた。
移植を受けられないまま合併症で脳死判定となった移植待機患者の臓器を移植に提供したいとの申し出が家族からあった、というケースも紹介。自分が患者の場合、あるいは患者の家族の場合、移植医療を受けるかどうかを、あらためて問いかけた。
「どうやって生きるか、ということは、どうやって死ぬか、ということ。医師を目指すみなさんにはこうしたことを真剣に考えてほしい」と呼びかけた。
小児成育外科の上野豪久(たけひさ)特任准教授は、小児肝移植や小腸移植について手術の画像などを示しながら解説した。
子どもの肝臓移植は「肝臓の病気になった子どもが、普通に大人になっていくためのほか、患者の家族が普通の日常を取り戻すために必要な治療だ」と話し、脳死移植のほか生体肝移植の方法があり、術後の合併症や免疫抑制剤の問題を乗り切れば、10年以上も普通の生活を送ることが出来るケースが多いと説明した。
米国留学を経て移植外科医になった経歴を振り返り、「留学当初は、病棟やオフィスで英語しか話せない中で、薬の名前が日本と違いオーダーすらままならず、誰もがトイレにこもり、泣くような日々が続く」とつらい実情を紹介。米国は様々な国籍の人が多く、外国人という差を感じることがなく、正社員登用の機会にも恵まれている、などと指摘した。
米国留学では「病棟業務に慣れるのに半年。1年後には仕事をこなし、2年経てば病棟でスタッフや看護師と雑談も交わせるようになって色々と楽しめる余裕も出てくる」などと述べ、留学を勧めた。
 |
| 大阪大学のセミナーで講義した上野豪久(たけひさ)特任准教授と平将生(まさき)講師(左から) |
| 前へ | 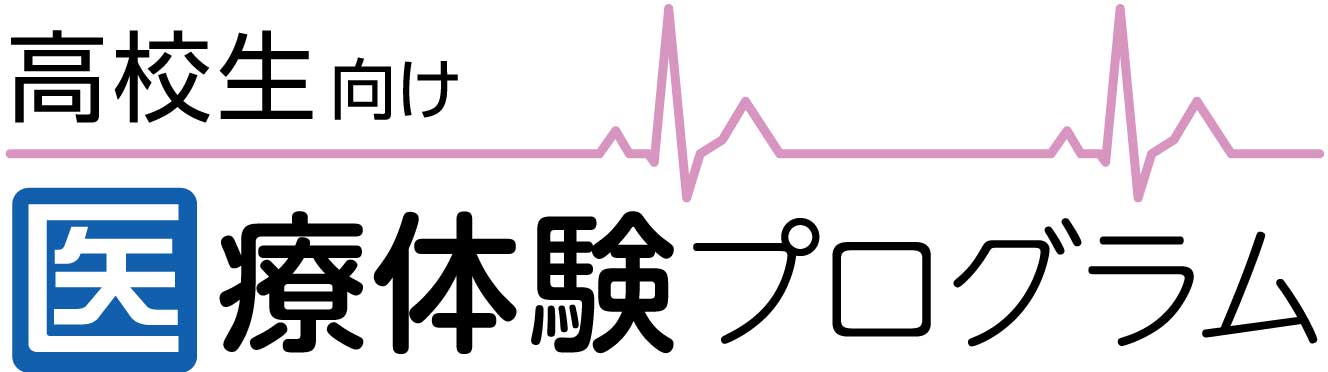 |
次へ |






