磯田道史さんら語る、歴史に学ぶコロナ対処...活字文化公開講座@二松学舎大学

国際日本文化研究センター教授で日本史家の磯田道史さんを講師に迎えた活字文化公開講座が3月18日、東京都千代田区の二松学舎大学で開かれた。昨年の創立145周年に歴史文化学科を開設した同大学が活字文化推進会議と主催し、読売新聞社が主管した。磯田さんは「歴史を学び、生きる力を高める~感染症の日本史~」と題して講演。さらに、二松学舎大学文学部の教員が専門の立場から感染症の歴史を語った。
磯田道史さん講演
「感染症の日本史」歴史と生きる力
歴史と生きる力はつながります。二松学舎大学を1877年に創立した三島中洲(ちゅうしゅう)は備中松山藩士、山田方谷(ほうこく)の私塾で学びました。
山田方谷は「理財論」で知られています。鉄を商品化して東京方面で直販するなどし、藩の財政をよくしていきました。「まわりを観察さえすればいくらでも豊かになる道はある」として「草を分けてみよ。道はある」と説きました。
草を分けて道が見えるようにするものが「人文知(じんぶんち)」です。本を読み、冷静に考えて価値あるものは何か、深いところからしっかり見詰め直す。その学問が経済を動かし、感染症や防災などで大事なのです。
福沢諭吉も「学者は国の奴雁(どがん)なり」と書いています。奴隷のガンですね。鳥のガンは群れで餌をついばむ時に1匹だけ首を上げて周りを警戒し、不意の難に番をする。学者の役割はこれだと。学者の議論は現在、そのときに効用が少ないかもしれないが、後になって効いてくる。冷酒や親の注意と一緒です。 
磯田道史さん(国際日本文化研究センター教授)
恩師の言葉が頭に
コロナが起きたとき、石弘之さんの著書「感染症の世界史」を読みました。コロナウイルスは1万年ぐらい前に家畜から人間に入り込み、今度の新型で大体7種類目です。
恩師の速水融(はやみあきら)先生が「必ず来るよ」と予言のように言ったことも頭にありました。速水先生は晩年、約100年前のスペイン風邪研究のため大正時代の新聞を集め始めました。あんなに人が死んでいるのに研究していないと。
コロナは速水先生が死去してまもなく起きました。最初に中国、数日後にタイで感染が起きたのを知り、スペイン風邪の教訓を発信しなければいけないと覚悟を決めました。
2020年3月3日に新聞の取材を受け、人文知の歴史的見地から、パンデミックが起きるとウイルスは思った以上に長く暴れること、移動の自由の制限が必要なことなどを話しました。
事態が長引く可能性については知り合いの落語家にも伝えました。高座がなくなるから、何とか暮らしていけるようにしなきゃいけないよと。ウイルスは変異して波状的に襲ってくる、移動と密集を避けながら、ワクチンによる免疫獲得を目指す必要があることなども発信しました。
経験したことがない事態になったとき、歴史学が極めて強い力を発揮します。
スペイン風邪の教訓発信、患者の個人史収集
スペイン風邪の致死率は変化しました。1918年8月~19年7月は1・22%でしたが、翌年5・29%に上がり、翌々年には1・65%となりました。
新型のウイルスが発生すると、最初、感染力はそう強くなくても強毒性です。次に強毒性で感染力も強いものに変化する。やがて致死率が低いものになり、みんながかかって終息に向かう。日本で最初の大規模な統計を持っているパンデミックはこういう経過をたどり、終息までに3年以上かかりました。
スペイン風邪の時のアメリカの都市別死亡者数で接触制限の有効性がわかります。セントルイスは早い時期に移動や密集などについて制限を行い、フィラデルフィアに比べて死者数が少なくて済みました。しかし、制限を解除した時期が早かったので感染が再燃しました。
コロナ禍でも景気対策などのために移動制限の解除が急がれる傾向にありました。危険を過小評価しがちな点に注意する必要があります。
スペイン風邪の患者の個人史収集も始めました。治される側はどんな気持ちでいたのか、対策を考えるうえで患者から見た医学史が重要です。祖父を亡くした京都の女学生は日記に「泣いて泣いて泣き尽くしました」と書きました。
最も資料が残っているのは秩父宮雍仁(やすひと)親王の患者史です。宮さまは症状が重篤で、治ってからも重い後遺症を自覚されていました。ご自身の証言が残り、遺書に「遺体を解剖に附(ふ)すこと」と記され、実紀が作られました。今回、コロナで重篤な場合、肺に重い後遺症をもたらしました。100年前と同じです。
歴史に「もし」はないと言われますが、僕は「もし」をやっています。例えば家を建てるときは設計図を何通りか作ります。古文書として残された史実のほかに、他の選択肢もあったはずと考える。大切なのは、心の内面です。なぜ起きたかということこそが、次に役に立つ歴史学なのです。
◇いそだ・みちふみ 岡山市生まれ。茨城大学助教授、静岡文化芸術大学教授などを経て現職。著書に「武士の家計簿」「天災から日本史を読みなおす」「感染症の日本史」など。近著は戦国、江戸、幕末の裏側を著した「日本史を暴く」と「徳川家康 弱者の戦略」。
感染症にどう向き合ってきたのか
中国 「温病学」治療専門化
 町泉寿郎教授(日本漢学史)
町泉寿郎教授(日本漢学史)
中国の伝統医学で流行性感染症と治療に関しては、2世紀末の「傷寒論」が有名です。病気の進行を6段階に分け、各段階に対応する漢方薬による治療が書かれています。傷寒は発熱性の流行病の総称です。
隋代で疾病の分類が細かくなり、宋代では「運気論」がはやりました。季節、天空の星の運行などが人体に影響を与える考え方です。明や清代に「温病(うんびょう)学」が発達し、感染症の治療が専門化します。
温病学の理論や治療は現代の中医学の形成に貢献しています。温病学は日本でも19世紀になるまでよく学ばれました。現代の中医学と日本の漢方は距離があります。この差を見る上で温病学への立ち位置がポイントになると思います。
日本 貴族の日記を参考に
 小山聡子教授(日本中世宗教史)
小山聡子教授(日本中世宗教史)
日本の古代・中世では、疫病は疫鬼(えきき)という鬼がもたらすと考えられていました。陰陽(おんみょう)師が定めた区域の外へ疫鬼を追い出す祭をするなどし、その効果の有無が貴族の日記などに記録され、後にそれらを参考に対処されました。つまり、疫病の原因を特定し、過去の経験から得た「知」を積極的に取り入れ、疫病に立ち向かおうとしていたのです。
現在、呪術による感染予防や治療は、前近代的・非科学的だと軽視されがちです。一方で、コロナ禍に江戸時代の史料にあったアマビエの護符が出まわりました。実際の予防効果はともかくとして、不安や恐怖を抑制する効果はあると考えられます。
感染症への対処についても、歴史から学ぶべきことは多いと言えるでしょう。
ヨーロッパ ペスト流行くり返す
 ヴィグル・マティアス准教授(近世日本医学史)
ヴィグル・マティアス准教授(近世日本医学史)
ヨーロッパでは中世以降、ペストが繰り返し流行しました。14世紀の流行は人口の3分の1の命を奪ったと言われます。ペストは神の怒りとされ、様々な信仰行為が行われました。流行の終焉(しゅうえん)を祈願する行列のほか、体から悪を追い出そうと裸の上半身を自分でむち打つ行為もありました。ユダヤ人が井戸に毒を入れたなどのデマが拡散され、ユダヤ人が迫害されました。
医学面では、当時の医師は悪性の空気によって伝染すると考え、全身を覆うガウン、手袋、眼鏡、くちばしのようなマスクなどの感染症防護服を装着しました。
15世紀には、港町で検疫所や隔離病棟などの隔離政策が制度化されました。当時の政策、社会混乱や不安、差別などがいまに通じます。
私小説や探偵小説の題材
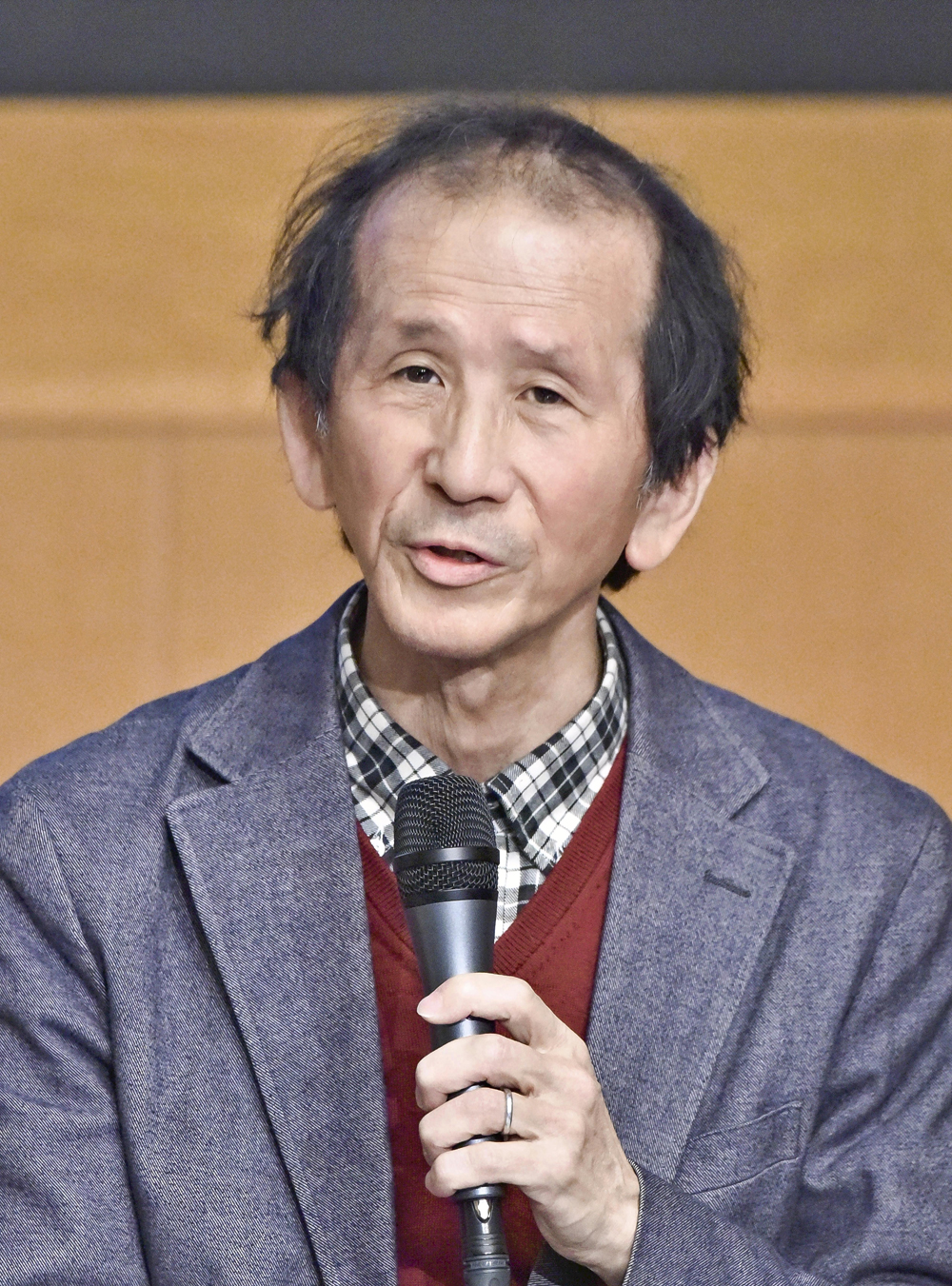 山口直孝教授(日本近代文学)
山口直孝教授(日本近代文学)
日本の近代文学で感染症は、作家が体験をありのままに書く私小説で取り上げられています。私小説の始まりと位置づけられる尾崎紅葉の「青葡萄(ぶどう)」はコレラ感染騒動を描き、志賀直哉の「流行感冒」、菊池寛の「マスク」と続いていきます。
一方、探偵小説ではウイルスが悪巧みや陰謀に用いられています。その先駆けである谷崎潤一郎の「途上」では、男が妻を殺すためにチフス菌への感染を企てます。小栗虫太郎の「二十世紀鉄仮面」では生物兵器として大都市圏でウイルスがばらまかれます。
私小説は記録に近く、探偵小説は現実の一歩先を描いています。突然流行が始まる感染症のとらえ方が小説において二極化しているのは興味深いところです。
「三者の了見考えて」
 聴講者からはさまざまな質問が寄せられた。主なやりとりは次の通り。
聴講者からはさまざまな質問が寄せられた。主なやりとりは次の通り。
――若い世代に向けて考え方の助言をいただきたい。
磯田 私がよく言うのは、「自分の了見、相手の了見、世間の了見」です。学問を見るときでも世の中を見るときでも歴史分析をする場合でも、カメラの三脚のように三者の了見を考えていただきたいと思います。
――長崎在住です。伝染病は長崎の方角から流れてくると言われたそうですが。
磯田 病気にもよりますが、江戸の頃は長崎に上陸して大阪付近に到達するのが数週間、ほぼ2か月で江戸に到達しました。それを媒介したのが港町でした。
――人文社会科学の意義は、専門を超えた視野を持ち、他の領域の専門家と協力し、かつ社会とのつながりを意識して難題に取り組むことと理解しました。
磯田 その通りです。分類、分析といった「分ける」学問ではなく、これからは「合わせる」学問が大事です。






