文字の重さ《記者のじぶんごと》

22.
![]()
自宅の近くにあった書店が次々に閉店し、外に出たついでに書店に立ち寄ることがめっきり減った。幸い職場のあるビルには小規模ながら一般書から文庫までそろえた書店があり、隣のビルには大型店が入っている。平日なら食事の帰りに新刊書を手にとったり、背表紙を眺めたりすることができる。
出版社や書店、出版取次などが参加して「秋の読書推進月間(仮称)」のイベントが開かれるという記事があった(2022年8月1日読売新聞朝刊)。2003年度に2万余店あった全国の書店が21年度は1万2000店を割った(日本出版インフラセンター調べ)ことが背景にあるという。「本を眺めて人と待ち合わせをしたくなる場としての魅力を広げようと、大規模な改装工事を行っている」という紀伊国屋書店新宿本店も紹介されている。本があるだけで時間をつぶせる人が減っているということだろう。
大学時代、待ち合わせ場所に必ず書店を指定する友人がいた。駅前の書店の文庫棚の前が多かった。大学までは徒歩で約15分。バスも地下鉄もあるのだが、彼と待ち合わせた日は必ず徒歩だった。
通りの両側に並ぶ古書店を一軒ずつのぞく。著者や古書についての彼のミニ解説を聞きながら回ると、キャンパスまで1時間近くかかるのはざらだった。彼にとっては定期的な巡回だったのだろうが、真夏と真冬は苦行に近かった。とはいえ、所持金がある日に買おうと狙っていた本が次のときには見当たらず別の店で見つけたり、さほど知られていない資料を思いがけぬ値段で手に入れることが出来たりして、いつの間にかこちらも古書店巡りに喜びを見出すようになった。
この友人と一緒に何人かで酒を飲み、私を含めた遠方からの通学組の終電がなくなると、東京・世田谷にあった彼の自宅に皆で泊まった。一戸建ての二階にあった彼の部屋は書棚や床だけでなく、二段ベッドが本で埋まり、部屋の外、廊下や階段の踏み板ひとつひとつにも本が積み上げてあった。漱石、鷗外は言うに及ばず、花田清輝、中村光夫、小林秀雄、植草甚一らの全集、単行本の間に体を横たえて、始発電車が動き出す時刻まで仮眠をとった。
大学を卒業して何年かして、彼は文芸評論家になった。こちらは社会部の記者で、日替わりの企画を担当していたとき、ネタに困ると彼に連絡してアイデアを拝借した。
「原稿用紙を手に入れにくくなって困っているんだよ」
その言葉をもとに記事を書き、彼にも談話を寄せてもらった(1995年9月15日読売新聞都民版「原稿用紙の危機 ワープロが台頭し学校使用も減少」)。ワープロがパソコンになり、スマートフォンから原稿が送れるようになってからも、彼は原稿用紙に手書き、ファックス送りというスタイルを変えなかった。
メールやSNSで送られる文字のおそらく大半は、紙に印字されずに消えていく。誉め言葉であれ悪態であれ、重さを持たない文字は紙に書かれた文字より遥かに速く、広く拡散する。そして、時を経るにつれ、最初にだれが書いたのか、知っている人はまれになる。紙に書く、紙で残すよりも効率や安全性は勝っているかもしれない。だが、その物差しですべてが測れるわけではない。
「秋の読書推進月間」の記事には、「インターネット書店の存在も、街の書店の脅威となっている」とある。インターネット書店は季節を問わずに快適だろうが、友人の解説を聞きながらめぐり歩くことはできない。一昨年急逝した友人、坪内祐三と街の書店で過ごした時間は、本当に贅沢なひとときだったと思う。
(橋本 弘道)
| 前へ | 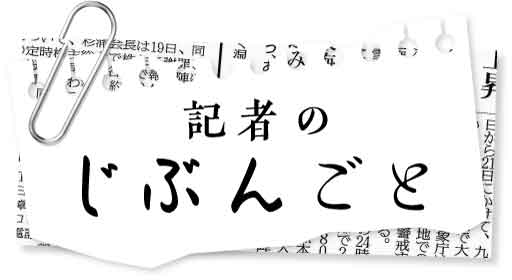 |
次へ |






