戦争独身は歯を食いしばって生きた《記者のじぶんごと》

12.
![]()
紅葉の名所として知られる京都市の常寂光寺は朝露で落葉が石に張り付いて赤いじゅうたんのようだった。1995年12月、「女の碑の会」の法要に取材で訪れたときのことだ。
「女の碑の会」は1926(大正15)年生まれの谷嘉代子元花園大学教授が「戦争独身が生きたあかしに」と呼びかけて1979年にできた。第2次世界大戦で大勢の若者が戦死し、彼らに見合う多くの女性は結婚の機会を失って戦争独身と呼ばれた。その数約50万人余りに及ぶ。会は常寂光寺に平和を願う「女の碑」を建て、1989年には共同墓を作って12月初旬に年1度の法要を開いていた。
その日は全国から約200人が集まり、亡くなった11人をしのんだ。19歳から家族を養った、編み物で身をたてた、看護師だった、阪神大震災で命を落とした、検体した⋯⋯。法要だが、同窓会に似ていた。会員に話を聞くと、同じ境遇の仲間とつながり、自分も入ることができる墓ができて喜んでいた。「1人で頑張ってきたから、死ぬ時も1人」。会員の平均年齢は当時69.5歳。女性1人だとお墓は買えず、実家の墓にも入りづらい事情があった。
戦後50年の記念行事として作家の田辺聖子さんの小説「おかあさん疲れたよ」(講談社文庫)の上下巻が配られた。1928(昭和3)年生まれの田辺さんが女の碑の会をモデルに本紙朝刊に連載した小説で、1995年6月に文庫化された。田辺さんは文庫の後書きに戦争独身への応援歌であることを記し、配布本の中表紙に直筆の署名と落款をしたためた。署名には上巻は緑色、下巻には紫色のカラーインクが使われており、会員たちへの思いがうかがえる。

法要の後、私は谷さんらと湯豆腐の鍋を囲んだ。戦争独身は多くが戦時中は軍需工場に駆り出され、戦後は自立を余儀なくされた。1986年施行の男女雇用均等法はカケラもなかった。「公営住宅の入居や銀行融資など社会や職場で多くのハンデがあったが、戦争独身は歯を食いしばって生きた。50年、100年先の人に伝えたい」。谷さんはそう語った。前月、谷さんは会の代表としてエイボン女性年度賞の功労賞を受賞した。会は戦争で大きな影響を受けた50万人の思いを代弁し、お墓のありようでは時代を先取りしていた。
私は自分の無知を恥じた。思い返せば、1970年代に通った女子中学・高校にも背筋を伸ばした戦争独身の教師が何人もいたのにその時は戦争独身という言葉を知らず、時代背景にも目を向けていなかった。嵯峨野で食べた湯豆腐は滋味深かった。たっぷりの薬味とともに戦争独身の矜持(きょうじ)も加わっていたのだと思う。
女の碑には故市川房枝さんの筆で「女ひとり生き こゝに平和を希(ねが)う」と刻まれている。共同墓は「志縁廟(びょう)」といい、5つある井戸状の納骨所に散骨する。おひとりさまとして道をひらいた谷さんもいまは志縁廟で眠る。会の法要は常寂光寺に託されて今年も10月に開催された。戦争独身個々人の戦後は続いている。
2021年12月8日で真珠湾攻撃から80年。世界では紛争が途絶えず、そのかげで難民や犠牲者と遺族、戦争独身が新たに生じている。
(笠間亜紀子)

| 前へ | 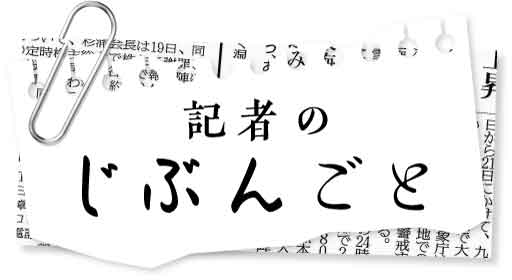 |
次へ |






