「紅一点」とは言わせない《記者のじぶんごと》

11.
![]()
スーパー戦隊シリーズは、1975年の「秘密戦隊ゴレンジャー」から現在放送中の「機界戦隊ゼンカイジャー」まで、ほぼ全作に「女性ヒーロー」を擁する男女共生の特撮ドラマである。それまで圧倒的に男性優位だったヒーローの世界に、第1作でモモレンジャーを投入した同シリーズは、84年、第7作「超電子バイオマン」で、女性を2人に増員するという快挙を成し遂げる。主に男児向けとされていたヒーロー番組としては、異例の決断だったと言える。
実は、少数派というのは3割を超えると組織を変える力になっていくそうだ(「女性を活用する国、しない国」竹信三恵子著、岩波ブックレット 2010年)。女性が「紅一点」であるうちは、世界は大勢である男性の論理で動く。一つしか用意されていない席に座り続けるためには、女性は男の論理を受け入れて「男らしい女性」、あるいは「名誉男性」的存在になるしかない。世界を女性も自然に活躍できるように変えるためには、ある程度の数が必要で、それが3割とされているのだ。だから国が掲げる「指導的地位に占める女性の割合」の目標も30%なのだろう。
5人のうち2人が女性となり、全体の4割を超えたことで、戦隊の世界は現実より一足早く、男女共同参画社会に近づく。もちろん母数はわずか5人だから単純比較は出来ないが、2021年になっても衆院選の女性当選者が全議員中9.7%と1割にも満たない現状と比べると、戦隊界の先進性に驚かされる。ちなみに、バイオマン放送の翌85年、日本は女子差別撤廃条約を締結し、国会で男女雇用機会均等法が成立している。

何より、1人が2人に増えたことで、彼女らが「女」としてひとくくりに分類されなくなったのは大きなメリットだろう。紅一点の場合、良くも悪くも女性は「女」という役どころから逃げられない。何をやっても「女の感性」「女性ならではの視点」「初の女性として」という言葉がつきまとう。単数が複数になったことによって、女性ヒーローたちは、男か女かを超えて「どんなヒーローか」を問われるようになっていく。バイオマンでは、活発でアーチェリー五輪強化選手の体力を持つイエローフォー(2代目、初代は殉職)とフルートが得意で敵とも心を通わせようとする心優しいピンクファイブという対照的な2人だった。
女性2人体制は、その後、様々な棲み分けを試みたり、再び1人体制に戻ったりしながら現在まで続いている。ゼンカイジャーのように、変身する女性は1人しかいない戦隊もあるが、もはや彼女が担うのは紅一点的な「女」の役割ではない。本作でピンクに相当するマジーヌは「オタク気質で引っ込み思案」という性差を感じさせない特徴の持ち主だし、2019年の「騎士竜戦隊リュウソウジャー」のピンクに至っては怪力で大食漢という、昭和なら「カレー大好きキレンジャー」のようなキャラクターだった。「女性だから」「女性として」と肩肘張らずに生きられる、しなやかな男女共同参画社会に、戦隊界はすでに到達している。
翻って現実を見るに、男女格差を測る世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で、日本は156か国中120位と心許ない順位であり、「女性が輝く世界」には、ほど遠い。それでも、今秋行われた自民党総裁選に高市早苗、野田聖子両候補の女性2人が出馬したことに、私は希望を感じた。ピンクとイエローではあるまいが、女性候補が複数になったことで、両氏周辺を飛び交う言葉から「女性初の」とか「女性代表として」という言葉が減ったように思えたからだ。
戦隊でも、バイオマンが先陣を切ってからリュウソウピンクやゼンカイマジーヌにたどり着くには、それなりに長い時間を必要とした。果たして日本が世界に誇るスーパー戦隊シリーズに続き、真の男女共生を現実のものと出来るかどうか。45作の記念イヤーに、特撮ヒーローたちはそんなことを私たちに問いかけているように思える。
(鈴木美潮)
| 前へ | 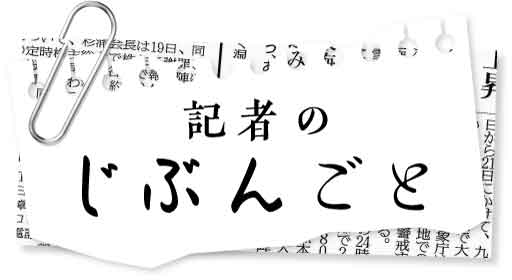 |
次へ |






