取り締まるのが警察だけれど《記者のじぶんごと》

09.
![]()
地下鉄に一緒に乗っていた知人が、「ウレタンマスクでしゃべるな」と見知らぬ乗客から怒鳴られたことがある。ウレタンマスクの飛沫を防ぐ効果が不織布マスクより劣るとして不織布マスクの着用を推奨する動きが盛んに報じられていたころである。立っている乗客が5、6人の比較的すいた車両で、知人のマスクもウレタンではなく布マスクだったが、会話を控えるべき車内で話をしていたのは事実だ。「すみません」と知人が謝ると、その中年の乗客は傲然とした顔つきで次の駅で降りて行った。
「自粛警察」から「マスク警察」まで、コロナ禍で本職の警察官以外の人たちが取り締まりに熱中した。お互いに監視し、非難し合った結果、新型コロナが収束に向かっているのなら、民間の警察をねぎらってもいいだろう。だが、成果のほどがはっきりしない一方で、ワクチンも特効薬もない不信と断絶が進行したことは間違いない。
「〇〇警察」という言葉を聞いて思い出したのが、約20年前、九州で勤務していたときに同僚の記者が書いた記事だ。主役は玄界灘の離島にある駐在所の警察官。この駐在さんは島に赴任した直後、駐在所前の急坂を手押し車を押して行き来する漁師たちに「なぜ車を使わないのだろう」と疑問をいだいた。実は漁師たちは無免許で、摘発を恐れて周辺にミニバイクを止めて駐在所の前だけ歩いていたのだ。駐在さんは無免許の36人を相手に免許教室を開く。お年寄りの中にはカタカナしか読み書きできない人もいた。教本に振り仮名を入れて教室を続け、2年後全員が合格した。駐在さんの本土への転勤が決まったとき、教え子の漁師が言った。「駐在さんは、島の恩人じゃ」
「なぜ無免許運転を摘発しないのか」「住民との癒着ではないか」。当時、SNSがあったら、次々と批判が書き込まれ、瞬く間に炎上していたことだろう。「警察警察」である。
だが、矢はそのままマスメディアに返ってくる。「いまはSNSがあるから」と言うとき、すでに炎上に加担していると指摘されても仕方がない。個人への誹謗中傷を代わりに受けて立つような記事を、ひるまずに書いていかなければならない。
昨年5月のゴールデンウイーク。大人も子どもも遠出を避け、筆者の自宅近くの公園は親子連れで混雑していた。午後の早い時刻、制服の警察官が公園に入ってきた。大人たちは警戒の目を向けるが、子どもたちは興味津々だ。
「お巡りさん、何かあったんですか?」。小学生が尋ねた。
「公園にたくさん人が集まっているという電話があったから、ちょっと見に来たんだよ」。警察官は笑顔で答え、そのまま公園を出て行った。
通報があったから、公園に来て様子を見る。これも警察官の重要な仕事ではある。新型コロナの感染拡大が一段落しているいま、本物の警察が別の仕事に人を割けるとすれば、幸いなことだろう。
(橋本 弘道)
| 前へ | 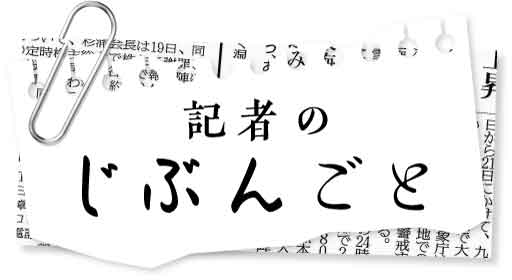 |
次へ |






