憂いの「ノーベルウィーク」《記者のじぶんごと》

08.
![]()
科学報道の最前線にいた時、ノーベル賞受賞者が発表される10月初旬の「ノーベルウィーク」ほど憂鬱なことはなかった。
たとえていえば、プロ野球日本シリーズの最終回の守備のようなもの。世間の注目度がいやがおうにも高まる中、うまく記事をさばいて当たり前。間違い(エラー)など許されないからだ。正直、「ボールよ、頼むから私のところには飛んでこないでくれ」と思っていた。自分の担当分野で日本人受賞者が出ると、特集ページや続報のため、寝食もままならない神経戦が1か月ほど続くからだ。
日本人の受賞ラッシュが始まったのは、2000年の白川英樹さん(化学賞)から。翌01年は野依良治さん(同)、02年は小柴昌俊さん(物理学賞)と田中耕一さん(化学賞)が同時受賞した。その後も日本人のノーベル賞受賞は怒涛のように続き、担当記者たちは歯を食いしばって10月を何とか乗り切るという気持ちが強かった。
その現場から離れた今、ノーベルウィークは打って変わって楽しい年中行事に変わった。なにしろ知的好奇心を満たしてくれる。たとえば今年は、新型コロナウイルス向けのm(メッセンジャー)RNAワクチンが当確だと予想していた。最近接種したばかりで、開発者は命の恩人といっても過言ではないからだ。
結果は大外れだった。現在進行形のmRNAワクチンの評価が定まるには、ちょっと時間が足りなかったかもしれない。しかし、mRNAを使ったこの手法はがん治療や再生医療、遺伝子疾患治療などにも応用でき、研究開発と臨床試験が活発になっている。医療の新時代を切り開いたことは間違いはなく、来年以降が楽しみだ。
そういえば、1年ほど前にコロナ感染の有無を調べるために初めて受けたPCR検査も、開発した米国のキャリー・マリスさんがノーベル化学賞を受賞した技術だ。サーフィンを愛し、研究者らしからぬ言動で知られたマリスさん。そのぶっ飛んだ半生記を読んでいたことに加え、取材対象だった医療や分子生物学の研究手法を激変させたPCR検査を自分が受けられたことが素直に感慨深かった。

そうなると連想はとまらなくなる。この原稿を書いているパソコンのリチウムイオン電池を発明したのは19年の吉野彰さん(化学賞)、まったく新しいがん治療法である「がん免疫療法」は18年の本庶佑さん(生理学・医学)、信号機や電灯のLEDは14年の中村修二さんら3人の日本人(物理学)......。我々は日常生活でも受賞者たちにずいぶんとお世話になっているのだ。
以上の受賞者たちとはちょっと違う意味でお世話になっていたのが、今年の物理学賞受賞が決まった真鍋淑郎さん。コンピューターによる気候変動予測を他に先駆けて行ったことが評価された。気候変動とは地球温暖化問題のことで、「不都合な真実」に科学のメスを入れてくれた真鍋さんには感謝したい。同時に、現場の記者たちは激務がもうしばらく続くだろうけれども、彼らの記事を通じて科学のおもしろさや醍醐味をもっと多くの人と分かち合えたらと思う。
(小川 祐二朗)
| 前へ | 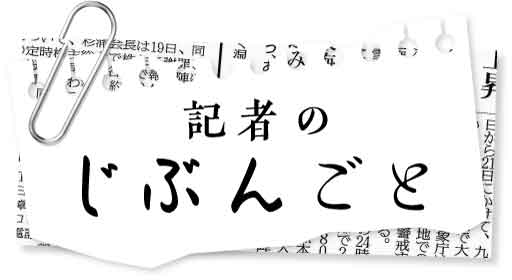 |
次へ |






