余白のないメモ帳《記者のじぶんごと》

32.
![]()
会って取材したばかりなのに、ノートを読み返して判読できない文字がある。自分の悪筆にうんざりしながら、ICレコーダーの録音を聞く。とはいえ、録音できる取材ばかりではない。そんなときは、相手の声の調子や仕草、服装など、ノートに書いていないことをひとつずつ丹念に思い出す。運がよければ言葉の細部が蘇ってくる。
一方で、メモ帳にもノートにも書かなかったのに鮮明に覚えていることがある。バブル景気のころ、夏の日に浦安近海のヨットの上で株の投資家の話を聞いた。「一昨日1億円損したが、昨日2億円取り戻した」と言いながら投資家は淡々とヨットを操っていた。間もなくバブルがはじけた。彼の消息は聞かなくなり、あのヨットも手放したのだろうかと思った。それ以降、潮風とヨットは私のなかではバブルの狂騒とその後の混乱に結びついている。
木材がくすぶるにおいをかぐと、阪神大震災の被災地を思い出す。360度広がるがれきの真ん中で、想像をはるかに超える惨状をどうやって伝えればよいか途方に暮れた。
大企業の不祥事の取材で、企業の役員宅を訪問したのは冬の初めの夜だった。不祥事には関係のない人だったが、企業内の事情を知るための取材だった。約束なしの訪問だったにもかかわらず、役員は初対面の私を自宅に上げてくれた。取材の最後、彼は「来月から子会社に出向するんです」と寂しそうに言った。「時間ができるから、社交ダンスを楽しもうかと。若いころから夫婦で習っているんです」
役員は廊下を挟んだダイニングにいた妻に声をかけた。「踊ろうか」
「お客さんがいるのに......」。妻は躊躇したが、なおも誘われておずおずと応じた。社交ダンスに全く縁がない私には、技術的なレベルはわからない。だが、2人が踊る姿は美しかった。ワルツの演奏が聞こえるようだった。
実は、その夜に聞いた話の内容は全く覚えていない。だが、2人のダンスだけは記憶に刻まれている。夫婦にその後何があったとしても、たいていのことは乗り越えられるのではないか、とそのとき思った。
コロナ禍と言われる時期が、とりあえず過ぎつつある。この3年間余り、リモートでのやり取りは会議にしろ、取材にしろ、余白のないメモ帳のようなものだった。言葉にしたことがすべてだった。
批評家の若松英輔氏が語っている。
「コロナ禍で普及したリモートシステムで話すとき、黙っていれば機械システムの故障かと感じます。でも対面で人間同士が会っていれば、間を取ったり、1分くらい互いに沈黙したりすることは普通にあります。話すことと同時に、静かに黙っていることにも気を配りたいと思うのです」(2023年5月9日読売新聞朝刊)
実際に会えば、沈黙していてもいろいろなことがわかる。相手の心情を察することもできる。だから対面がリモートに勝ると言いたいわけではない。対面かリモートか、それを選ぶ余裕が生まれたからこそ、どちらの場合もメモ帳に余白をたっぷりとり、その場で語られなかったことにも気持ちを向けたいと思う。
(橋本 弘道)
| 前へ | 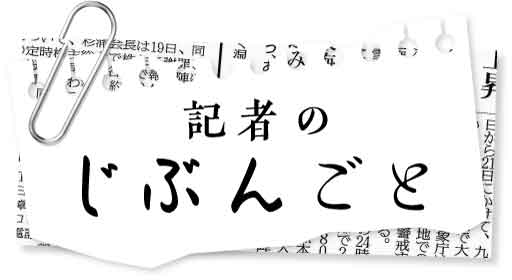 |
次へ |






